地域貢献への使命感と熱意で緩和ケア病棟を開設元緩和ケア部門長 佐野広美
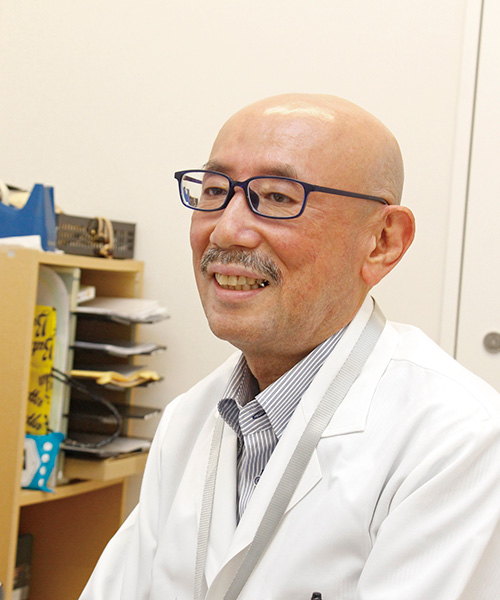
地域貢献を使命に、緩和ケア病棟開設への機運高まる
今や日本人の2人に1人ががんになる時代。医療技術の向上によって、がんと共生しながら日常生活を送る人も珍しくないが、治療の甲斐なく亡くなる人が多いのも事実である。そんな終末期を迎えたがん患者を受け入れ、苦しみを和らげるための医療を提供する施設が、緩和ケア病棟だ。
野村病院が緩和ケア病棟を開設したのは、2011年(平成23年)のこと。当時はまだ緩和ケアに対する世の中の認識が未成熟で、大病院でさえ終末期のがん患者への対応に苦慮していた時代である。そんな行き場のない患者を受け入れることは、医療の提供を通じて地域とともに歩み、地域に貢献することを使命としている慈生会野村病院にとって大きな意義がある——。そう考える野村理事長の信念の下、緩和ケア病棟開設への機運が高まったのである。
とはいえ、全133床のうち約1割の12床を緩和ケアに充てるのは、組織体制の面でもスタッフの意識の面でも、簡単にできることではない。そのため、医療部門と看護部門はいうまでもなく、事務部門や購買部門スタッフも加わった一大プロジェクトを発足させ、病棟開設に向けて動き出した。折から野村病院では、事業拡大のために増改築が行われており、緩和ケア病棟もその一環として位置づけられることとなった。
もう一つ、病棟開設に向けて大きな力となったのが、野村病院全体に満ちていた、未来に向けて前進していこうという勢い、ムードのようなものである。野村病院が緩和ケア病棟を持つ意義は大きく、地域社会に与えるメリットは計り知れない。その一員であることへの誇りと使命感が、全員を突き動かしたのである。
キーマンを中心に、病棟開設に向けた取り組みを推進
その中でも、病棟立ち上げの中心となったのは、言うまでもなく医師と看護師である。その核ともいうべき存在が佐野広美医師だ。佐野先生は2005年に消化器外科医として野村病院に入職した。
「それまで数多くのがん患者を診察し、手術を行ってきました。その中には、いくら手を尽くしても救えなかった患者さんも数多くいます。その経験から、いつしか緩和ケアに興味を持ち、緩和ケアの道に進みたいと思って野村病院に来ました」と佐野先生は語る。その思いを聞いた野村理事長は、当面は外科の責任者として働きながら、緩和ケア病棟開設向けて準備していくことを提案した。
こうして外科医として働くうち、近隣の大病院で根治不能となった患者の行き場がなく、地域の問題になりつつあることが明らかになってきた。そんな折、野村理事長から緩和ケア病棟開設に向けて動き出すようにと伝えられたのである。
「そのときは、いよいよ具体化するのかと思うと同時に、改めて責任の重さを実感しました。それまでは、一般病棟で地域のニーズに応えて終末期がん患者を受け入れ、未熟ながら自分なりの緩和ケア診療を実践してきました。しかし、いざ12床をお前に預けると言われると、本当に自分にできるだろうかと心配になりました。一方で、こんな機会は滅多にないと思い、気持ちを引き締めて準備に入りました」と佐野先生は当時を振り返る。
まず行ったのは、野村病院における緩和ケア病棟のコンセプトを決めることだ。幹部と一から議論を重ねるとともに、プロジェクトメンバーとともに他施設の見学のため九州にまで足を運んだり、三浦副院長(当時)から医療倫理を学んだりした。
もう一人、緩和ケア病棟の開設に向けて力になったのが、佐々木看護部長(当時)である。佐々木部長は都立駒込病院で緩和ケア病棟を立ち上げたことがあり、その経験は野村病院にとって極めて貴重だった。そもそも緩和ケア病棟には何が求められるのか、病棟で働く看護師はどう選べばいいのかなど、持てる知識と知見を惜しみなく提供した。
本当の苦労は病棟開設から始まった
こうして2011年12月、多くの人の協力によって野村病院に緩和ケア病棟が開設された。しかし、本当の苦労はここから始まったのである。
緩和ケアとひと言でいっても、患者一人ひとりにはその人なりの人生観があり、物語がある。最後まで諦めずに治療を受けたいという人もいれば、ただ安らかに最期を迎えたいという人もいて、一律ではない。それは患者の家族も同様で、ときには患者本人の意向とは異なる要望を受けることも珍しくない。従って、医師として、あるいは看護師として、点滴一つ行うにも、カテーテルを入れるにも、何が最善かを問われるのが緩和ケアなのだ。そのむずかしさについて佐野先生は、「例えば、医師としてこの患者さんにはもう少し医療を施すことができるのではないかと思っても、看護師からは“そこまでやる意味があるんですか"と疑問を呈されたりして、最初の1年くらいは意見が対立して関係がギクシャクすることもありました。そんなときは、私一人で11人の看護師と戦っているような気持ちになりました」と打ち明ける。
そんな状態が続いていたとき、佐野先生は須藤院長(当時)から思わぬ言葉をかけられた。「佐野先生は1対11と言うけれど、最近の様子を見ていると1+11になっているんじゃないですか」その言葉を聞いたとき、救われる思いがしたと佐野先生は振り返る。
地域の緩和ケアに対する理解も深まる
野村病院の緩和ケア病棟について語るとき、もう一つ欠かせないのが地域との関係だ。緩和ケアを提供するためには、地域の在宅診察医や医療、介護スタッフとの連携が欠かせない。それはネットワークの構築という面だけでなく、意識の共有も含まれると佐野先生は指摘する。
「緩和ケア病棟を立ち上げたとき、単なる看取りの場ではなく、病状に応じて退院を促し、住み慣れた自宅で療養してもらうことを方針にしました。そのためには、地域の医療関係者と連携しながら、患者さんを自宅でケアする体制が欠かせません。しかし当時は、医療従事者の中でも緩和ケア=看取りの場という理解が一般的で、野村病院の方針に疑問を呈する人も少なくありませんでした。それに対して、退院後は様子を見て再入院することもできるという私たちの考え方を根気よく説明し、実践していきました。その過程を通じて、地域における緩和ケアに対する理解が深まり、共有することができたと思います」
こうした試行錯誤を経ながら、緩和ケア病棟では、患者の苦しみを少しでも和らげようと、購買部門の協力も得ながら四季折々のイベントを開催した。
「流しそうめんやサンタクロースなど、ちょっとやりすぎかなと思うくらい、スタッフ全員が協力していろいろな試みをしました。また、患者さんが亡くなって3ヵ月後に遺族の方に出すグリーフレターも、それぞれの想いを手書きし、感謝されたこともありました」。
地域のニーズに合わせ病棟を変えていくことが必要
多くの関係者の熱意と努力によって開設した野村病院の緩和ケア病棟は、今では地域にとってなくてはならないものとなっている。そして、開設から10年以上がたつうちに、野村病院と大学病院などの高度医療機関、在宅診療医や医療、介護スタッフなど地域の医療関係者との関係は、より強固なものとなっている。
「その中で今でも忘れられないのは、入院の相談を受けたまま自宅で亡くなった方のご遺族がわざわざ挨拶に来られて、“先生にいつでも入院できるから、安心しておうちで療養してくださいと言っていただいて、気持ちがとても楽になりました。いざというときは野村病院があるから、安心して家で最期を看取ることができました"と言っていただいたことです。その言葉を聞いて、緩和ケア病棟をやっていて本当に良かったと思いました」と佐野先生は述懐する。患者とその家族だけでなく、地域にとっても、野村病院は終末期のがん患者を受け入れてくれるという安心感。それによって野村病院の緩和ケア病棟は、地域における緩和ケアのレベル向上に大きく貢献したのである。
一方で、現状に満足することは許されないと佐野先生は述べる。
「結核病院から始まって、一般病院、総合診療体制へと病院の姿、機能が変化してきたように、これからも地域のニーズに合わせて変化していくことが求められていると思います。野村理事長がよくおっしゃっているマーケット・インの考え方によって、患者が病棟に合わせるのではなく、患者や地域のニーズに合わせて病棟を変えていくことが必要です。人手不足など、これからもいろいろな問題に直面すると思いますが、緩和ケア病棟を立ち上げたときのあの熱気、使命感があれば、野村病院はますます発展していくと思います。これからも地域になくてはならない緩和ケア病棟、そして野村病院としてあり続けてほしいですね」。
※『地域と共に歩む野村病院』-創立70周年の先を目指して-からの転載
